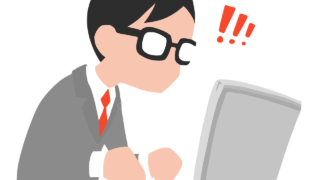どうも、Tomatsuです。
いまビジネスパーソンに最も注目されている資格ランキングNo.1の「中小企業診断士」。
最もAI代替可能性が低い士業(0.2%!!)として日経新聞に紹介されたのがまだ記憶に新しいですが、一方で、なくなる・廃止される可能性が噂されていたり、使えない・役に立たない資格との指摘も多いです。。。
まず第一に申し上げたいのは中小企業診断士は「なくなりません(廃止されません)」。
このような噂はガセネタですので注意下さい。
また、資格が「使えない・役に立たない」というご指摘に関しては、有資格者としては「いやいや、そんなことねーよ。ってか前提条件も置かずに『役に立たない』っていう指摘はあまりにも解像度低すぎでは?。。。」と思う一方で、目的によっては診断士取得が遠回りにもなりますし、こういった指摘が多い理由も分かります。
そこで、今回は中小企業診断士資格がどのようなケースにおいて「役に立たないのか?」または「役に立つのか?」について考察したいと思います。
- 中小企業診断士資格が気になっている方
- 中小企業診断士を受験中の方
あくまでTomatsu個人の主観に基づく考察であることを予めご了承下さい
中小企業診断士が役に立たないは本当か?

中小企業診断士が「役にたたない」とされる最も大きな原因は
資格取得 = それだけで食えるわけではない
からです。
この点に関しては多くの方々が考察しておりますが、私自身も確かにそうだな~と思います。
なので、「1,000時間の勉強時間を費やして資格をゲットできたらその後は飯を食うのに困らないバラ色の人生が待っている」と思っている方にとっては悲報ですが、その考え方は改めた方が良いのかなと感じています。
「資格取得≠飯が食える」は独占業務がないから?
資格取得がそのまま飯を食えることに繋がらないのは「中小企業診断士には独占業務がないから」なのでしょうか?
個人的に「これは関係ない」と思っています。
なぜなら独占業務を有する下記のような難関士業でも満足に食べられていない方々が一定数いらっしゃるからです。
- 弁護士
- 公認会計士
- 税理士
- 社労士
- 行政書士
一方で、独占業務が無い中小企業診断士でも独立していて年収数千万円以上というプレーヤーもかなり多くいらっしゃいます。
以上から、独占業務の有無は飯が食えるか否か?の要因にはならないことが分かります
結局は自分で営業する気があるか?どう差別化するか?がポイント
独占業務があろうがなかろうが、口をパクパクして待っていただけでは仕事は入ってきません。
つまり結局は、自分自身の力で営業力を身につけて顧客開拓する気があるか否か?が重要ということです。
また、診断士の勉強では経営戦略、財務・会計、運営管理、経営法務、情報システム、など経営に関する幅広い知識が手に入るのは事実ですが、これらが実際のクライアント様へのコンサルティングにすぐ使える知識かというとそうではありません。
自分自身の競争力を高めるために、資格取得後も専門性や提供価値を身につけるための自己研鑽を継続しなければなりません。
ですので「営業力を身につけるつもりがない」「自己研鑽を続けるつもりがない」と考えている方にとっては「資格取得は役に立たない」可能性が高いと言えます。
これは他の士業(弁護士・税理士など)についても同じことが言えます。
取得したら自動的に食えるようになる魔法のような資格は存在しないということですね。
言い換えると営業力があって提供価値がある人に資格は不要
これは言い換えると、既にクライアントに売れるサービス(提供価値)があって、自分自身の力でゴリゴリ営業できる人にとっては「資格取得はかえって遠回りになる」とも言えます。
というのも自分自身で「経営コンサルタント」と名乗るのに資格の有無は関係ないからです。
診断士試験は1年で最短合格できた場合でも平均1,000時間という勉強時間を要します。
この膨大な時間を働きながら捻出するのは思ったよりもハードです。
もちろん診断士はビジネス全般について体系立てて学べる良い手段ではありますが、自分で食べていく自信がある場合はすぐに独立して実務を通じた試行錯誤・レベルアップに時間をあてた方が良いとの見方もできます。
逆に中小企業診断士はどんな場合、役に立つのか?

では診断士資格の取得のメリットは何なのでしょうか?
幾つかポイントを挙げてみます。
[診断士資格取得の利点]
- 最初の実績が作りやすい(独立・複業につながる)
- クライアントの評価が自動的に上がる
(企業内診断士の場合)
- キャリアアップ(昇進、部署異動、転職)
最初の実績が作りやすい(独立・複業につながる)
診断士資格の一番のメリットは「最初の実務実績が作りやすい」ことです。
幾つか理由がありますが、大きいものとしては下記が挙げられます。
- 先輩診断士からの紹介を受けられる
- 公的機関(経営専門家派遣)からの紹介を受けられる
少しイメージして頂きたいのですが、実績も無い新人コンサルタントから営業をかけられた場合、中小企業の社長はどう思うでしょうか?
めちゃくちゃ不安ですよね。
まず、何ができるのかも分からないし、実力を表せる実績もない。
ただでさえ余裕のない中小企業としては「実績が十分にあり、課題解決に導いてくれる可能性が最も高いコンサルタント」からアドバイスを受けたいと思うはずです。
このことから分かる通り、よっぽど突出したノウハウがない限り最初のクライアントを探すのは死ぬほど難しいのです。
一方で、診断士資格を取得しておけば、先輩診断士・公的機関からの案件を受注しやすく、比較的容易くたやすく「実績・ノウハウ」が得られます。
個人的には、これが診断士資格の何よりの価値だと思っています。
正直、先輩診断士や公的機関からの受託案件は単価が低く美味しい仕事は少ないかもしれません。
ただ、実務経験を経て得られる実績やノウハウは何物にも代えがたいです。
実績さえ得られれば2件目、3件目の新規開拓営業のハードルはグンっと下がりますし、この積み重ねが独立・複業診断士としての成功に繋がるのです。
ご自身に売れる商品・サービスは無いものの、独立や副業コンサルとして活躍したいと考えている方は、診断士資格を取得して、先輩や公的機関からの仕事を通じて実績を積んでいくのも良いオプションだと思います。
クライアントの評価が自動的に上がる
次のポイントは「クライアントからの評価が自動的に上がる」です。
どういうことでしょうか?
私は現在、クラウドソーシングを活用してWeb系コンサルティング案件を請け負っているのですが、営業を開始してすぐにライバルが300人以上応募していた高単価案件をかなり簡単に受注することができました。
クライアントになぜ私を選んでくれたのか?とお尋ねした所、最も大きな要因は私のプロフィール蘭に中小企業診断士資格(未登録ですが。。。)と書いてあったこと、とおっしゃっていました。
他にも「当ブログの実績やWeb周りの知識があったこと」など幾つか理由はあったようですが、ブロガーやWeb系人材は数多くいるけど、それに加えて中小企業診断士である人は稀有であるということがポイントだったようです。
更にこのクライアント様は、将来的には会社の戦略立案や財務周りなどのアドバイスも求めたいとのことで、かなりの期待感をもって発注してくれたことが分かります。
以上ようにクラウドソーシングのプロフィール蘭や名刺等に中小企業診断士というラベルを貼ることで受注環境がグンっと良くなることも多いです。
これも診断士を取得する一つのメリットと言えるでしょう。
(企業内診断士の場合)キャリアアップ
最後のポイントですが、診断士資格の取得はサラリーマンの「キャリアアップ」にも役立ちます。
なので、独立・複業志向でない方にとっても大変おすすめの資格と言えます。
では具体的にどのようにキャリアアップに役立つのでしょうか?
幾つか例を挙げてみます。
- 昇進
- 希望部署への異動(経営企画・新規事業開発など)
- コンサルティング会社への転職
これは有名な話ですが、金融機関ではそもそも診断士資格の取得が昇進の要件になっている場合もありますし、他にも私の知り合いの企業内診断士は経営企画や新規事業開発部署への異動が決まったりしています。
また、官民問わず、コンサルティング会社への転職の要件(というか推奨資格)として中小企業診断士資格が挙げられることも多くなってきました。
このように資格取得が何かとキャリアアップにつながることが分かりますので、何かしら自己啓発をしたいんだけど何をやれば良いか分からない、という方はとりあえず中小企業診断士を目指してみるというのもアリだと思っています。
まとめ
以上、長々と考察を述べてきましたが、いかがでしたでしょうか?
診断士資格の取得が必ずしも目的達成の最適手段とは限りませんが、使い方によっては相当協力な武器になるのも事実です。
はっきり言って働きながらの勉強はかなりキツイですが、少しでも興味がある方はぜひ挑戦してみて頂きたいと思います。
ご質問・コメントなどあればどしどしお願いします。
それでは最後まで読んで頂きありがとうございました。